本の特送便 梅書房 > > 渡辺治著作集 第6巻 日本国憲法「改正」史 憲法をめぐる戦後史・その1
|
978-4-8451-1720-8
渡辺治著作集 第6巻 日本国憲法「改正」史 憲法をめぐる戦後史・その1
|
||
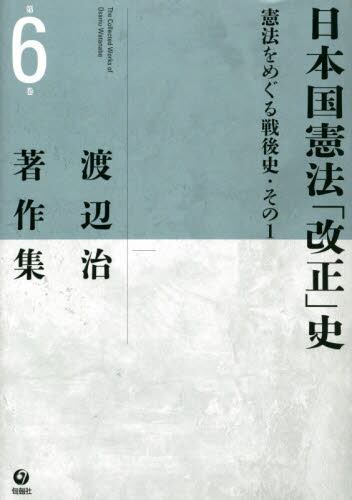
|
||
|
¥7,700
|
||
|
||
| お問合せ・ご注文 口コミを見る(0) |
| 【内容】 憲法九条を維持したままでの「再軍備」、鳩山・岸内閣による改憲策動、六〇年安保闘争による明文改憲の挫折、解釈や法律で憲法規範の改変を行なう「解釈改憲」、―改憲を軸に、戦後憲法を歴史的に分析。日本国憲法が戦後政治の争点となり続けたという特異な状況に着目し、憲法改正をめぐる攻防を戦後政治支配と統合のあり方をめぐる対抗の焦点として描く。 |
| 【目次】 刊行にあたって 解 説 はしがき 序章 本書の課題と視角 一 なぜ憲法「改正」史を検討するのか――問題関心の所在 二 方法に関わる若干の問題 第一章 改憲前史(一九四五年) ――敗戦直後における支配層の明治憲法改正構想 一 〝おしつけ憲法〟論と憲法制定過程 二 敗戦直後における二つの国家改革構想 1 内務官僚の秩序再編構想 2 外務官僚の憲法改正構想 三 支配層の明治憲法改正構想 1 近衛グループの明治憲法改正構想 2 美濃部・宮沢ならびに憲法問題調査委員会の憲法改正構想 第二章 吉田内閣期の憲法政策(一九四八―五四年) ――現行憲法制度の原型の形成 一 〝吉田路線〟とは何であったのか 二 戦後日本の国際的枠組みの形成と吉田の限定的役割 1 憲法第九条の現実的意義 2 アメリカの対日政策の転換と講和方針をめぐる対抗 3 吉田の限定的役割 三 吉田内閣の安保・再軍備政策の独自性と憲法 1 再建すべき軍隊の性格についての吉田の独自性 2 再軍備の方式ならびにスピードについての吉田の独自性 四 吉田内閣における改憲消極政策の形成 1 「戦力」概念を中心とする政府の解釈論の確立の経過 2 改憲消極政策選択の要因 3 再軍備合憲論の諸類型の登場 4 裁判上の〝試練〟と一応の確立 五 吉田内閣下での日本型司法審査制の形成 1 問題の所在――「特殊日本型憲法訴訟」の形成 2 日本国憲法への司法審査制の導入をめぐって 3 憲法学におけるアメリカ司法審査制の紹介の傾向 4 占領権力による制約と司法自制 5 秩序の創出期の司法審査と伝統的法理論 6 田中コートにおける特殊日本型司法審査制の形成 第三章 五〇年代改憲とその挫折(一九五五―五九年) ――復古的改憲と社会との乖離 一 改憲派の台頭による支配層内の二つの潮流の形成 1 改憲派の台頭 2 支配層内の二つの潮流の対抗と特徴 二 五〇年代改憲論の形成とその特質 1 自由・改進両党憲法調査会の活動 2 日本民主党の結成――改憲派の政治的結集 3 改憲構想の特質 三 改憲派の政権掌握と五〇年代改憲の昂揚 1 鳩山内閣の発足 2 自由民主党の結成と党内の二潮流 3 自民党憲法調査会内における対抗の発生と改憲構想の手直し 4 改憲気運のクライマックスから急速な退潮へ 四 五〇年代改憲の挫折とその要因 1 五〇年代改憲の終焉 2 五〇年代改憲挫折の要因 第四章 六〇年代改憲とその挫折(一九六〇―六四年) ――明文改憲から改憲消極政策への暗転 一 戦後型統治への転換と支配層の新たな分岐 1 〝安保〟の衝撃と、統治方式の転換 2 権威的改革派の結集と支配層内の新たな二潮流の対抗 二 政府の憲法調査会の活動 1 憲法調査会内の〝前哨戦〟 2 第三段階の審議の進め方をめぐる攻防――第五五回総会 3 改憲論の変容 4 改憲論の停滞打開のための新理論の拾頭と改憲派の混乱 5 高柳「理論」の攻勢 6 改憲派・消極派の最後の攻防 三 最終報告書の完成と六〇年代改憲の終焉 1 池田の改憲消極姿勢の鮮明化と党内分岐の激化 2 報告書の提出をめぐる諸勢力の反応 3 六〇年代改憲の終焉 第五章 憲法の定着と解釈改憲(一九六五―七九年) ――七〇年代憲法状況 一 解釈改憲と憲法的枠組みの承認 1 間歓的噴出した改憲の動き――明文改憲の終息 2 憲法状況の変化に対する諸説 二 高度成長による社会変化と新しい憲法状況の現出 1 憲法意識の変容 2 憲法的価値の実現をめざす運動の展開 3 社会的支配構造の成立と憲法「定着」の限界 三 解釈改憲政策と憲法第九条 1 憲法第九条の規範的拘束力の重し 2 第九条下の安保と自衛隊についての国民的合意形成の企図 四 憲法体系を前提にした支配の展開 1 裁判の変化と司法部門の政治的役割の拡大 2 自治体の変貌 五 オイル・ショック以後の社会的支配構造の確立と憲法 1 企業を中心とする社会的支配構造の確立 2 社会状況の全般的変化 3 憲法状況の変化のきざし 第六章 八〇年代改憲の台頭(一九八〇年―現在) ――明文改憲と解釈改憲の競合 一 新たな改憲策動の急浮上とその背景 1 変化の端緒――有事立法問題 2 奥野改憲発言と自民党憲法調査会の再開 3 改憲諸組織の活性化 4 八〇年代改憲の規模とその背景 二 八〇年代改憲の新しい形態 1 〝タブーの打破〟論 2 「下から」の大衆運動と民主的機構の利用 三 新しい改憲イデオロギー 1 改憲イデオロギーと「防衛」イデナロギーの混在 2 〝護憲的改憲〟の論理 3 高度成長社会批判を根拠とした改憲論 4 新しいナショナリズ 四 支配層内部の分岐と解釈・明文改憲 1 対抗は〝狂言〟か――対抗の性格 2 支配層内部における分岐の形成過程 3 支配層の二つの分派の対立の性格とその効果 五 八〇年代改憲の現局面 1 国家体制の権威的再編成の進行 2 明文改憲派の迂回戦術の展開 あとがき 改題にかえて・本書執筆の頃 |
| [本巻の検討対象] 本巻には、『日本国憲法「改正」史』(以下、『改正史』と略す)を収録した。 筆者が『改正史』を書くにあたっての問題関心がいくつかあった。一つは、当時、改憲阻止の運動と理論の中で支配的であった、憲法空洞化論―憲法は安保体制と支配層の政策により空洞化が進み、憲法の条文は維持されたままその理念は蹂躙されているという議論―は、憲法現象の把握として間違っていること、また運動上も正しい方向を示すものではないという点を、憲法をめぐる攻防を通じて、明らかにしたかったことである。つまり、憲法は空洞化論が言うような名ばかりのものになっているわけではない、運動に支えられて現実の政治や社会を規制する力をもっているということを立証したかったのである。 そのため、とりわけ、改憲に対する五〇年代の戦後民主主義運動、頂点としての安保闘争が五〇年代改憲を挫折させただけでなく、保守政権に憲法の枠組みを前提にした政治を余儀なくさせたことを解明した。改憲ができなくなったため、しかも憲法裁判運動も続発する状況で、政府も、自衛隊が憲法九条に違反しないと抗弁するために、自衛隊の行動にそれなりの制約を設けざるをえなくなったことなどがその典型例であった。 そもそも、憲法が支配層の政策によって「空洞化」しているのであれば、支配層が八〇年代に入って、改めて改憲策動に乗り出す必要はない。総じて、戦後史は、支配層の思惑の一方的貫徹の歴史でも逆に人民の運動の前進の歴史でもなく、支配層と被支配層の対抗の歴史であることを描きたかったのである。 問題関心の二つ目は、序章でも検討した「解釈改憲」という概念について、その有効性は確認しつつ、一九六〇年代以降の保守政治における改憲消極政策の中でも、九条を安保体制のもとに組み込むための厳密な意味での「解釈改憲」と同時に、ある限定内であれ、憲法の枠組みを前提にした支配を余儀なくされた側面の両方があることを検証したかった点である。 両方相俟って、筆者は、『改正史』において、憲法が運動の力で現実を規制する一定の力を有し機能していることを明らかにしたかったのである。 こうした問題関心にもとづいて書かれた『改正史』に若干の意義があるとすれば、それは以下の点にある。 第一は、戦後日本では、日本国憲法の扱いが戦後政治の争点となり続けたという特異な状況に着目して、憲法改正をめぐる攻防を、戦後政治支配と統合のあり方をめぐる対抗の焦点として描いたことである。 その際、戦後政治においては、日本の進路と国民統合のあり方をめぐって支配層内に常に二つの分派が台頭、対立しあい、政治過程はその攻防を通じて展開したことを明らかにした。一九五〇年代には、日本の国際社会での位置をめぐって、米国に従属・依存して国際社会への復帰を図ろうとする主流派と大きな意味では「西側陣営」の一員でありつつ対米「自立」と大国としての復活を志向する反主流分派に分かれたが、この両派は、国民統合においてはいずれも戦後憲法の体制に不満をもち復古主義的統合に親近感をもっていた。ところが、六〇年安保条約改定をめぐる安保闘争の昂揚により復古主義的方向が断念された六〇年代以降になると、支配層内の対抗は、国民統合のあり方をめぐるそれに移行し、戦後社会の変容に対応して経済成長重視の路線を追求する「戦後型統治派」と、より権威主義的統合をめざす「権威的改革派」の対立に変容した。そして、憲法維持か改憲かは、そうした支配層内の対立を貫く争点であり続けたのである。 第二に、『改正史』では、戦後支配層はのべつまくなしに改憲を指向したわけではなく、国民の強い「反復古」「平和」憲法支持の意識と運動を顧慮して改憲に消極的な姿勢をとった時代が長かったこと、改憲派が政権を掌握した時代は長くは続かなかったこと、その意味では、戦後憲法をめぐる歴史は、憲法改正の挫折の歴史でもあったことを明らかにしたことである。 第三に、第二の延長線上であるが、『改正史』では、一九四八年の第二次政権以降六年に及ぶ吉田茂内閣の時代と、六〇年の池田勇人内閣以来の二〇年あまりの時代という、戦後支配層主流が改憲消極政策を採用した二つの時代に焦点を当て、なぜ支配層が憲法を〝自己の支配の最良の外皮〟とは認めないまま、改憲消極政策を維持したのか、その要因を検討することを通じて、戦後政治の特質を浮き彫りにしようとしたことである。 その際、改憲消極政権として同一の性格をもった政権と見做されている、吉田内閣期と、池田内閣期以降の政治には、憲法に対する態度・方針では同じく改憲消極政策とはいえ決定的な違いがあることを明らかにした。すなわち吉田内閣は国内統治のあり方では、日本国憲法の構想する政治体制を変え復古主義的統治の志向をもっていたが、池田内閣以降の政治は、国民統合上、復古主義を清算し、憲法の枠組みを前提とした統治を志向したことである。 |